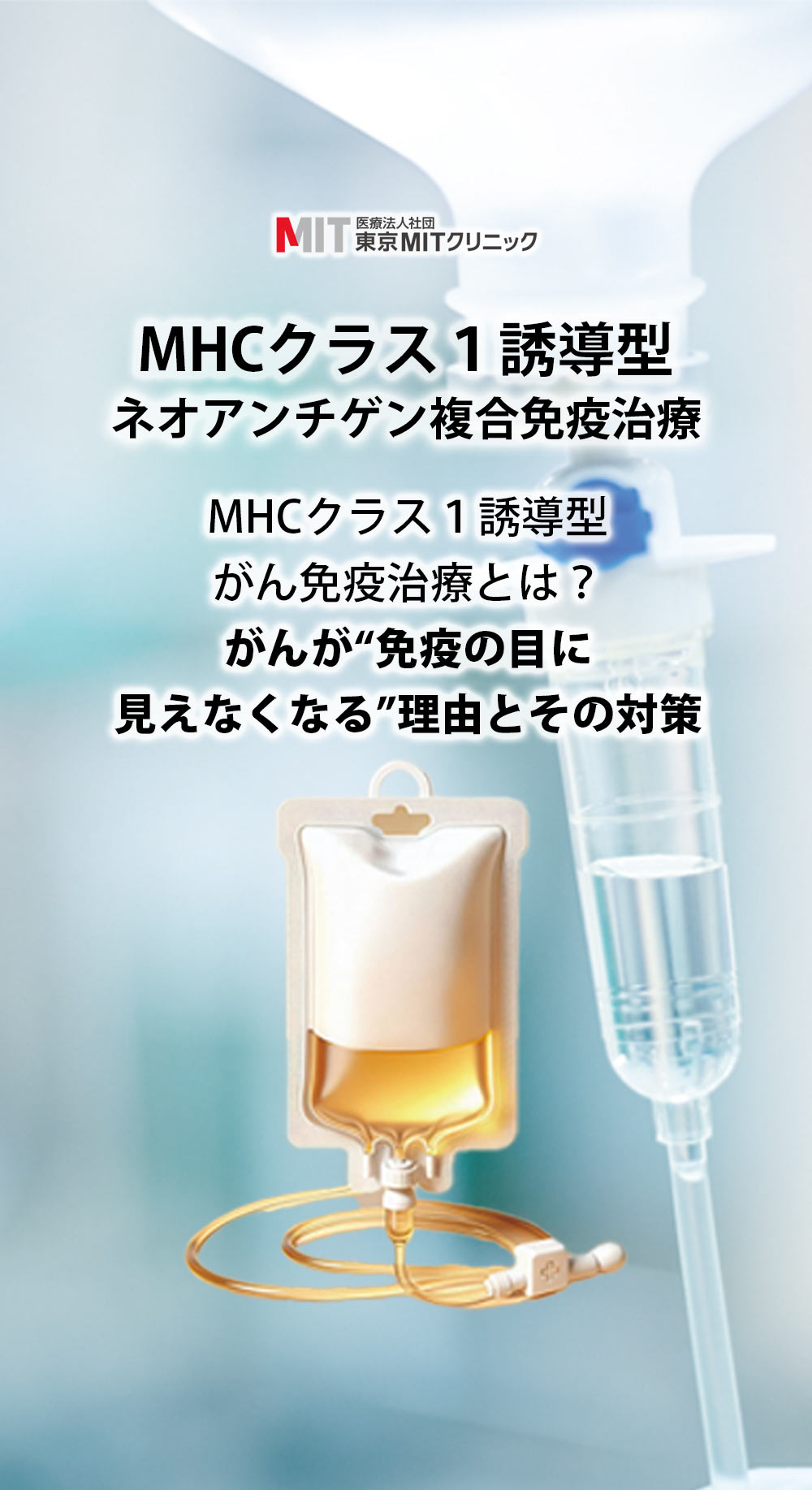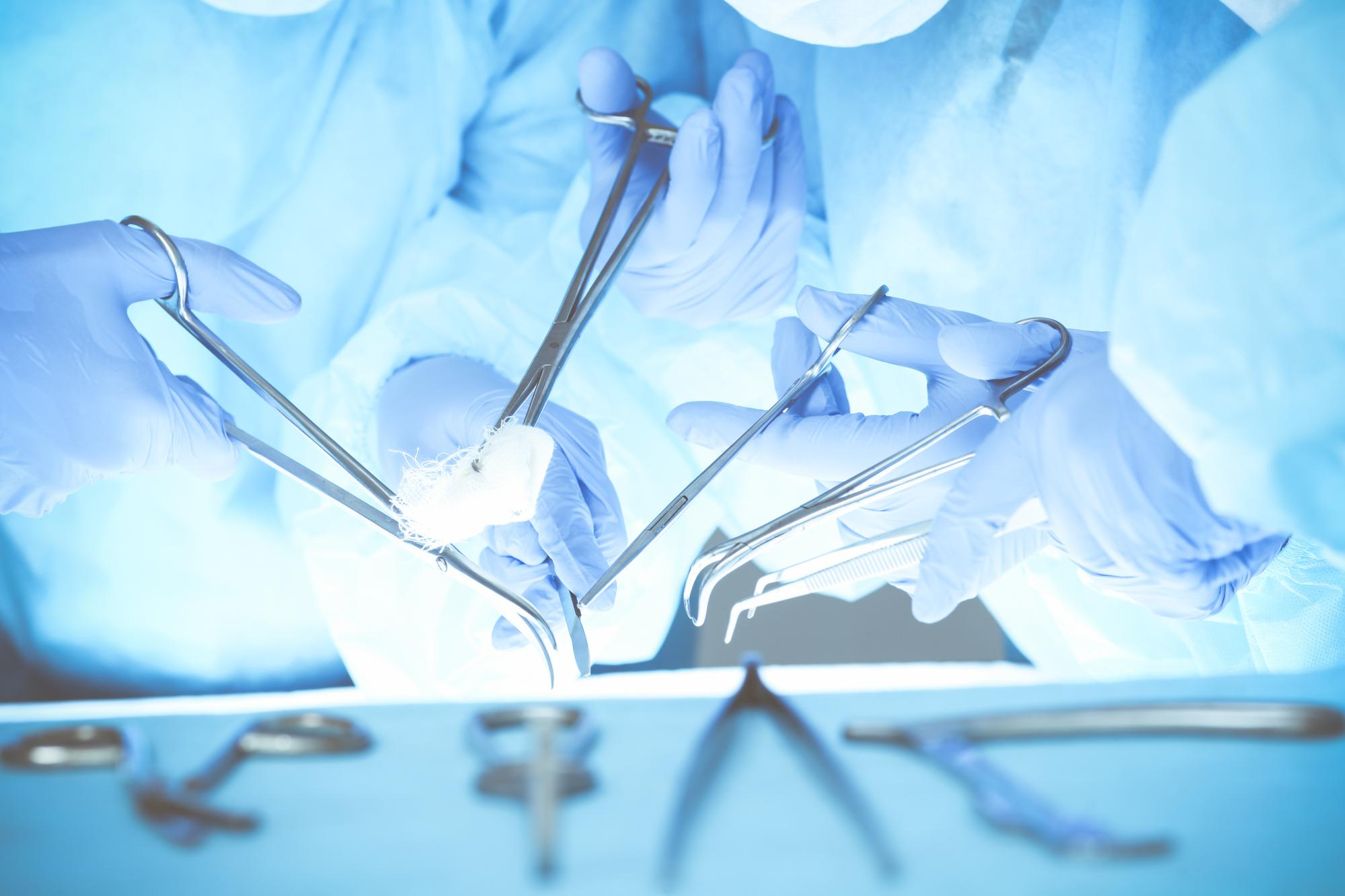MHCクラスI誘導型がん免疫治療とは
- 対象:MHCクラスIの低下が関与する可能性がある進行がん等。適応は医師が個別に判断。
- 方法:外来での静脈点滴。所要時間は目安で約60分(体調や併用療法により変動)。
- 併用:標準治療や免疫療法と併用を検討可能。安全性や順序は診療時に決定。
MHCクラスIとは
- MHCクラスIの低下が関与する可能性がある進行がん等。適応は医師が個別に検討。
- 外来点滴(目安:約1時間前後。体調や併用治療により変動。
- 標準治療や免疫療法と併用を検討可能。
- 安全性と順序は診療時に判断。
進行がんでMHCクラスI(主要組織適合性抗原)が低下した可能性がある患者さんに対し、点滴(約1時間)で“見えにくいがん”を免疫に再提示する戦略です。
標準治療や免疫療法と併用検討可な、MHCクラスI(主要組織適合性抗原)とは、あらゆる細胞の表面に備わる分子構造であり、その細胞が「正常か、異常か」という情報を免疫細胞に伝達しています。
しかし、がん細胞が進行がんに至るとMHCクラスIは表面から隠れてしまい、免疫細胞(とくにT細胞)による攻撃から巧妙に逃れるようになります。
MHCクラス1誘導(点滴)とは
MHCクラスI誘導では、特殊なペプチドや免疫誘導剤によってMHCクラスI分子の再発現を促し、あらためて免疫細胞(T細胞)にがんの存在を知らしめる役割を果たします。
いったん見失ったがん細胞を再び見える化することで、停滞していた免疫反応を再び動かす極めて重要な一手となるのです。
初診当日の実施について
適応判断がつき準備が整えば、当日の実施を提案する場合があります(症状・検査結果により異なります)。
進行がんになると、ほとんどのがん細胞で表面のMHCクラスI発現が低下してしまいます。
だからこそ、「進行がん」と診断されたら待たずに一手を打つという発想が重要です。
つまり、MHCクラスI誘導は、治療計画の初期段階から検討される選択肢の一つです。
MHCクラスI誘導点滴の本質と役割
MHCクラスI誘導は、がん細胞を免疫に再び敵として認識させるための重要な役割を果たします。
その結果、MHCクラスIの再発現が免疫細胞(T細胞)の標的認識を強力に向上させ、がん免疫治療の本質的な起点を再構築します。
なお、従来の免疫療法では、この見える化技術は未確立でした。
しかし、いまや患者さん自身がMMHCクラスI誘導の「重要性に気づくべき時」が来たと考える背景や考え方がここにあります。
MHCクラス1誘導点滴とその所要時間
当院で用いる特殊ペプチド/免疫誘導剤と乳酸化リンゲル(250mL)を用い、静脈点滴を約1時間で行います。
MHCクラスI誘導は、臨床研究から導かれた独自の特殊ペプチド/免疫誘導剤と、乳酸化リンゲル輸液(250ml)の混合剤を一時間前後点滴で静脈投与すれば終了です。
まれに、点滴針の挿入部に小さな内出血が生じた、といった軽微な所見か認められることを除き、当院の診療記録では1997年10月24日〜2023年10月31日までの期間、重篤な有害事象は確認されていません
加えて、標準的に実施される抗がん剤治療やその他の免疫療法との併用を検討可能です。相互作用や順序は診療時に個別判断します。
MHCクラスI誘導を行う前に知っておきたいこと
この治療は、進行がんにおいてMHCクラスIが消失している状態に対する免疫治療戦略です。
以下のようなケースでは、事前に知識を持っておくと良いでしょう。
- 早期がんでMHCクラスIまだ発現していると考えられる場合 →
慌てずに、精密検査「Risk Checker(リスクチェッカー)」を実施した後、治療戦略を検討するのがよい - 抗がん剤や放射線治療との併用 →
がん細胞のストレス応答により、MHCクラスIの再発現が促されると一部研究で示唆 - チェックポイント阻害薬の効果が出にくかった症例 →
MHCクラスI誘導により再び反応性が得られる可能性がある
他のがん治療との併用で、MHCクラスI誘導はさらに活きる
MHCクラスI誘導は単独でも意義のある治療ですが、他の治療法と併用することで、より高い相乗効果が期待されると一部研究で示唆
- 免疫チェックポイント阻害剤との併用
がん細胞を見える化することで、これまで活躍できなかったT細胞療法が再び力を発揮する可能性。 - 自然免疫を利用した治療との併用
NK細胞療法・NKT細胞療法・樹状細胞療法などとの併用により、免疫全体を包括的に活性化。 - 抗がん剤・放射線治療との併用
がん細胞のストレス応答によりcの発現が増強され、T細胞の免疫応答が強化される可能性。
こうした併用により、免疫が効く状態を強化し、長期的ながん制御が目指せると考えられます。
なぜ今、MHCクラスI誘導型がん免疫治療なのか?
がん免疫療法は近年大きく進歩しましたが、「効く人・効かない人」が分かれる原因の一つに、MHCクラスIの消失があります。
がんが見えないままでは、どれほど高度な免疫療法でも働かないのです。
MHCクラスI誘導は、この「見えなくなったがん」を再び免疫に見える化することで、免疫の力を引き出す起点になる治療です。
近年は免疫チェックポイント阻害薬、抗がん剤、放射線治療などとの併用による相乗効果も一部研究で示唆され、「がんの見せ方を変えること」が今後の免疫治療の鍵になると考えられています。
東京MITクリニックでの治療実績
当院では、MHCクラスI誘導型がん免疫治療を、以下の体制で提供しています
- 延べ29,000件を超えるがん治療に関する臨床データ
- 高度精密血液検査「リスクチェッカー」による治療前評価
- 副作用の少ない非侵襲的治療設計
- 海外からの相談・受診希望にも対応中
よくある質問(FAQ)
Q. どんな人が対象ですか?
A. MHCクラスIの低下が関与する可能性がある進行がん等について、診療情報を踏まえて医師が個別に適応を検討します。
Q. 受け方と所要時間は?
A. 外来での静脈点滴が基本です。所要時間は目安で約60分(体調や併用療法により変動)です。
Q. 標準治療や免疫療法と併用できますか?
A. 併用を検討可能です。安全性や順序、期間は診療時に個別判断します。
Q. 副作用はありますか?
A. 一般的な注意点や体調変化の可能性は事前にご説明し、観察体制のもとで実施します。重篤な有害事象の有無は観察期間・定義により評価します。
最後に
がん細胞が免疫から隠れてしまう──
その仕組みを突き止め、再び免疫の目に“見える化”する。
それがMHCクラスI誘導型がん免疫治療です。
もしもあなたが、進行がんやステージ4、再発に悩んでいるなら──
この治療が、次に選べる道になるかもしれません。
治療の仕組みや適応範囲をわかりやすくまとめた情報ページはこちらです
👉 MHCクラスI治療の詳細を見る
※当院で提供するMHCクラスI誘導型がん免疫治療は、保険適用外の自由診療です。治療方針・費用などについては医師にご相談ください
(※)エビデンス 治療担当・院長:宇野克明の研究/臨床実績。がん免疫治療の研究/臨床応用(外来診療)開始以来、およそ29,000例の治療経験症例を有しています。1997年10月24日〜2023年10月31日
最終更新日:2025年8月8日
監修:宇野克明(医師/東京MITクリニック)